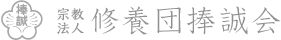彼と毎日あいさつできるように
ある朝、駅から歩き始めてなんとなく思い出したことがありました。それは捧誠会で私のするべきことについて至らなかったところを、ある人からびしばしと言われて、「なんだってそんなことを人から言われなければいけないんだ」と、かなり不満にも思ったり、「いや、私の方に落ち度があったんだからこちらが改めればいいんだ」と思い直したり、また不満に思ったりと、何度かそんなことを繰り返していました。
そして、ある朝、それを思い出していました。そんなことはそのうち忘れてしまうだろうといったんは思ったんですが、その時はすぐに、「それは、そうじゃないんじゃないか。それは私の問題であって、相手がどうとかじゃなくて、自分の方が考えを変える、すなわち至らなかったことを反省すればいいんだ」と気がつき、「次からは気をつけよう」と気持ちを切り換えました…というか、切り換えさせていただいたと言った方が正しいと思います。
そして、とても気が楽になりました。
毎日通っている道の途中に、市の福祉センターというのがありまして、そこを通りかかると、よく顔を合わす人で、私より少し若い人が「おはよう」と声をかけてくれました。すぐに「おはようございます」と返事をしましたら、「元気?」とまた言ってくれましたので、「お陰さまで元気です」と言いますと、「僕も元気だよ」と言ってくれました。少し障がいのある方だと思うのですが、いつもは何も言わないというか気がついてくれないのに、どうしたんだろう思いましたが、もしかしたら「私の顔が穏やかないい顔になっていたのかな」と少し嬉しくなりました。
しかし、次の日からはまた私には気がついてくれませんので、また振り出しに戻ったのかなぁという感じでした。
今度はこんなことがありました。
私のいつも通っている道路なんですが、道幅を広げ、歩道をつける工事のところで、舗装したばかりの浸透性アスファルトの歩道に、カッターでまた筋をいれてあったんです。「何やってんだろうな、また無駄使いをして…」と批判の気持ちを持ちましたが、いくらなんでも工事の専門家がやるんだから、そんなドジは踏まないだろうくらいには思っていました。
次の日、またそこを通りかかって、「あっ、そうか。目の不自由な人のために黄色のパネルを埋め込むための準備なんだな」と思いましたら、その次の日、やはり一部に黄色のパネルが埋め込んでありました。
次の朝、またそこを歩きながら昨日までの自分のことを思いだし、簡単に人のことを決めつけ、侮ったり軽蔑してはいけないんだなと気がつきました。
当たり前のことかもしれませんが、結構自分はこんなことをしてきていたんだなあと改めて気がつかせていただき、これからは気をつけようと思いました。私の心がいかに高いかが伺い知れた出来事でした。
人を見て侮る心ある時は己が心も濁りいるなり
そうしましたら、また例の彼に会いまして、目が合ったものですから、今度はこちらから「おはよう」と言いましたら、「しばらくぶりだね」と返事が返ってきました。結構いつもすれ違っているのに、私にはまったく気がつかない日がほとんどなんですが、私が何かに気づいて反省した時に限って彼が私に気がついてくれるような気がしました。もしかすると神様が至らない私を導くために彼を遣わされたのかなどと思ったりしています。彼と毎日「おはよう」と明るくあいさつできるように努力したいと思っています。
A男 会員の手記を基に一部編集したものです。